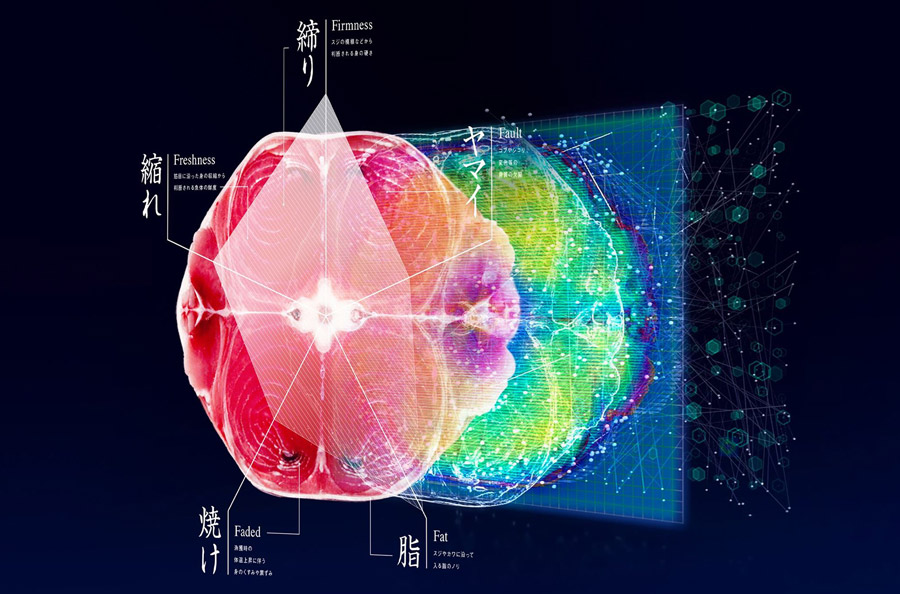-プロジェクトの今後の展望を教えてください。
今後の具体的な展開としては、1月からTUNA SCOPEによるAI品質判定を行ったマグロが、ニューヨークとシンガポールでの提供が開始されました。
さらに3月には、プロジェクトが水産庁の「水産物輸出拡大連携推進事業」に認定されました。2020年は、水産庁の支援を受け、AIによる品質判定を受けた高品質なマグロを世界中に輸出していくための準備を進めています。
私は、このTUNA SCOPEが世界に拡がっていくことには、さまざまな面で重要な価値があると考えています。一つ目は、世界中どこでも、誰もが美味しいマグロを食べられるようになるからです。世界には、日本の職人のように長い人生をかけてマグロを見続けてきたプロの目利きの職人はいません。よって、日本ほどレベルの高い品質判定を通さず、人々の食卓にマグロが届けられているのが現状です。しかし、AIにより、世界中に日本の職人の能力を拡げていくことで、世界中の人たちが日本の目利きが入った美味しいマグロを食べることができるようになります。これは、日本人としても嬉しいことです。
また、もう一つの理由は「TUNA SCOPE」は、世界的な課題である「マグロの資源問題」の解決にも役立つのではないかと考えているからです。
私たちが日常生活で食べる普通のマグロは、主に重さや量で取引されています。ゆえに乱獲で問題となる漁では「量」を重視し、たくさんの数を獲るために幼魚も含めて群れをまとめて大量捕獲しています。さらに、一度にまとめて捕獲された魚は網の中で暴れまわるため、体温の上昇で身がヤケてしまったり、魚体に傷がついたり、なかには死んでしまうこともあります。その結果、著しく鮮度が落ちてしまうのです。
「TUNA SCOPE」を導入し、世界共通の品質基準をつくり、判定する仕組みをつくることができれば、獲り手側の意識を「質」重視に変えていくことができるだろうと考えています。大量に捕獲するよりも、マグロの品質、鮮度を保つために1体ずつ丁寧に獲ろうとする獲り手が増えていくでしょう。丁寧にマグロを獲る漁船のマグロが市場で評価され、みんながおいしいマグロを食べることができ、資源も安定することにつながっていく。人も資源もビジネスも、Win-Winの関係を築けるのではないでしょうか。
TUNA SCOPEのプロジェクトの始まりは個人の想いでしたが、それが拡大し、今では社会の課題を解決する可能性を持った事業へと拡大しつつあります。今後はこのプロジェクトで得られたノウハウを活用することで、匠の技をAIの力で継承する活動として、水産業はもちろん、他のさまざまな分野にまで拡大していきたいと思っています。
TUNA SCOPE:
https://tuna-scope.com/jp/
リリース:
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0424-010044.html